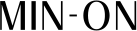[ NEWS ]
ルベン・ラダ氏(歌手・打楽器奏者) インタビュー
ルベン・ラダ インタビュー
◇歌手・打楽器奏者
インタビュアー:ピアソラ研究 斎藤充正
ラダ:もうショーは観てくれたのかな?
――初日の川崎と二日目の鎌倉を観て、二日目の方がもうお客さんのノセ方をわかってきたなという感じを受けました。
ラダ:二日目の方がよかったね。ブラジルでは「観客席の調教師」と呼ばれているよ。お客さんは自分が引っ張っていくものであり、例外はないんだ。コロナ禍でみんなで歌えないのは残念だけどね。
――これまで、どれだけの国に行かれましたか?
ラダ:ヨーロッパのほとんどの国、ラテンアメリカのすべての国で演奏してきたけど、日本にはずっと来たい、まったく今までと違うお客さんに自分の音楽を届けたいと思っていたんだ。ラテンアメリカの人たちにとっては、ラダのショーというのはパーティー、サッカーの試合みたいなもので、そのためにもいつも優秀なミュージシャンを連れて回っているよ。私の音楽は形式に縛られないワールド・ミュージックだからね。ロックンロール、(ブラジルの)サンバ、アルゼンチンの(フォルクローレの)サンバ、ボサノヴァ、カンドンベ、メレンゲ、サルサ、ルンバ、あらゆる要素があるんだ。私にないのはクラシック音楽だけ。だからここまでくるのは大変だったよ。ロックのアーティストにはロック・ファンが付くし、タンゴを歌えばタンゴ・ファンが聴く。でもラダのレコードを聴いたら眩暈がするだろうね、ロックで始まってチャカレーラ(フォルクローレの一種)で終わったりするから。
――それでラダさんのファンは付いてきてくれるようになりましたか?

ラダ:時間はかかったよ。オーパ(盟友ウーゴ・ファトルーソらとのバンド)で録音したレコードが出た時、タワー・レコードに行ったけど、どのコーナーにもなくてね。プロデューサーのアイルト・モレイラが「ブラジリアン・ジャズ」という名称を付ける必要があったんだ。ミルトン・ナシメント、ジルベルト・ジル、ピアソラ、ルベン・ラダ、ウーゴ・ファトルーソ、エルメート・パスコアルなどが、既定のジャンルにとらわれないワールド・ミュージックを演奏し始めた最初の世代なんだ。日本公演にあたっても、日本の人たちにどんな音楽を演奏すると説明すれば良いかって聞かれたけど、ラテン音楽はもう世界中で知られていて、説明する必要はなくなったよ。
――今までに共演したアーティストで印象に残っているのは?
ラダ:敬愛するレイ・チャールズのオープニング・アクトを務めた。メキシコではスティング、(ブエノスアイレスの)ルナ・パークではトム・ジョーンズ。自分は決して世界的に有名なアーティストではないけど、音楽家には好かれているよ。自分がナンバー・ワンだと考えるアーティストもいるけど、私はそれを冗談にして表現するんだ。
――ツアーも半分終わりましたけど、実際に日本で演奏してみてどうですか?
ラダ:お客さんは素晴らしい。敬意を示してくれて、楽しんでいないように見えても、心の中で喜んでいるというのが伝わってくるね。「踊りましょう」と声を掛けると、周りを気にしてから立つのがステージからわかるから。同じ日本人でもアルゼンチンやブラジルにいる人たちはもっとラテン的だけどね。
――ステージでも仰っていたけど、78歳という年齢にはみんな驚くんですね。それなりに大変でしょうけど。
ラダ:実は背中が潰れていて、長い距離は歩けないんだ。私の身体の調子はステージに上がることで良くなり、下りたらまた悪くなる。ステージで死ねれば本望だよ。そのために生まれてきたからね。とにかく傷みはあるけれど、あらゆる材料を使って、少しでも前進しないと。
――ステージを続けていることもそうですけど、アルバムも毎年出している、そのエネルギーはどこから来ているんでしょう?
ラダ:それが自分のできる唯一のことだから。まぁ料理もできるけどね。料理は芸術だよ。
――そもそもカンドンベとは?
ラダ:ブラジルのサンバだとスルド、サルサならボンゴやティンバレスを使うのに対し、カンドンベでは3つのタンボール(太鼓)を使う。小さいのがチコ、大きいのがピアノ、即興ができて自由度が高いのがレピーケ、その3つをそれぞれ棒で叩く。3つのタンボールを持って通りに出て呼びかけることをジャマーダと言うんだ。家にいてそれを聞きつけた人々が、家にあるタンボールを持って隊列に加わり、30人にも40人にもなる。昔のモンテビデオには、閉ざされたところに住んでいる奴隷の黒人たちに、演奏するための休暇が与えられていて、カンドンベはそこから始まった。今は毎年カーニヴァルがあって、どこの地区にもカンドンベのチームがあるよ。
ウルグアイはブラジルとアルゼンチンという大きい国に挟まれて吸い取られているから、ミュージシャンもウルグアイで生きていくのはとても厳しい。自分やウーゴ・ファトルーソのように、成功したいと思ったらアルゼンチンに行き、そこからほかの中南米の国々へ、というのが大体の道だね。ホルヘ・ドレクスレルが映画音楽でオスカーを取り、私もグラミー賞をもらい、ウーゴ・ファトルーソは日本を含む世界中で演奏し、やっと世界中で我々ウルグアイ人のCDが出回るようになったり、ウルグアイの音楽がどういうものか知ってもらえるようになってきた。
――最近の話題というと、(2016年に)ローリング・ストーンズのミック・ジャガーと会われました。
ラダ:“ロボさん”(タンボールのフェルナンド・ロボ・ヌニェス)の誕生日だったんだ。ロボは築150年の古い家に住んでいて、ミックはローリング・ストーンズのツアーでウルグアイに来ていた。黒人音楽を演奏するストーンズは、自分にとってイギリスで唯一のロックンロール・バンドだよ。ロック・ミュージシャンが、ツアー先で何をするかというと、ジャマイカに行けばボブ・マーリーを訪ね、サンバを知りたければファヴェーラに行く。ウルグアイといえばカンドンベだ。ロボ・ヌニェスは世界中のミュージシャンの間でよく知られているよ。タンボールの作り手としてだけでなく、カンドンベの学校のような人で、黒人の歴史にも詳しいしね。太鼓があって、黒人の衣装があって、黒人の歴史が感じられるものがたくさんあるので、ロボの家はいつもパーティーのようなんだ。ミックが来た時には「サティスファクション」をカンドンベのリズムで、皆で演奏したよ。
――会ってみた印象はどうでした?
ラダ:1時間だけだったからわからないけど、感じもよかったし、ウルグアイの黒人音楽に興味があることはよくわかった。ヨーロッパでも北米でも、音楽資源というものは枯れているよね、優れた音楽家はいるけど。音楽はいつも同じところを回っていて、でもラテンアメリカには別のリズムがある。彼らが自分たちにないものがあるところに行った時、頭をオープンにして新しいものを取り入れるために、ミックもウルグアイではカンドンベを知ろうとしてやってきたんだろうね。
――その時のことをアルバム『ネグロ・ロック』で歌にしましたね。

ラダ:「ロボとミゲル」ね。夏の暑い日で、ミックが来ることは知らなかったんだけど、カンドンベとロックンロールがあるというので、息子たちと出掛けることにした。ストーンズのコーラスのベルナルという、たぶんフランス人の黒人女性がロボに会いたがっているという話で、でも私は本当は行きたくなくて。テレビでサッカーの試合をやっていたし、着替えるのも嫌だったからね。午前2時を過ぎてもベルナルは現れず、もう来ないから帰るよと言ったら誰かがドアをノックして、開けたら身長2mの黒人女性の後ろにミック・ジャガーがいたんだ。ロボは「ミゲリートがオレの誕生日に来てくれたよ、嬉しいな」って。そんな素敵な夜だったからこの曲を作ったけど、詩的な歌詞を付けたら息子のマティアスに怒られたよ、「嘘つきだな、行きたくなかったくせに」ってね(笑)。
――50枚以上残してきた中で、一番お気に入りのアルバムはどれですか?
ラダ:「ラス・マンサーナス」が入った最初のアルバム(『ラダ』)かな。もう5世代もの人々が歌ってくれているので。この曲と「フィガーリのためのカンドンベ」は学校で子供たちも歌ってくれているんだ。最高のアルバムではないけれども、このレコードで初めてみんなが自分のことを知ってくれたから、過去を忘れてはいけないという意味でこれを選んでみた。私にとって良いレコードといえば、グループでのものだね。トーテムやエル・キントやオーパ、ほかのミュージシャンと一緒にやることによって、自分の違う面を出せる。自分のソロだとスタイルがばらけるからね。グループでやるとスタイルが定まる。
――最後に、日本のファンにメッセージがあれば。
ラダ:ラテンアメリカの音楽を聴き続けてください。日本に演奏しに来たミュージシャンたちは、本当に喜んで帰ってくるんだ。皆さん本当に優しいし、素直だし、ラテンアメリカのように政治に不正があったりとかしないし、長い歴史があって、音楽だけでなく文化全体が成熟していると感じているよ。自分たちはまだ200年ぐらいで歴史が短くて、まだオムツを履いていて(笑)、成長している段階だからね。